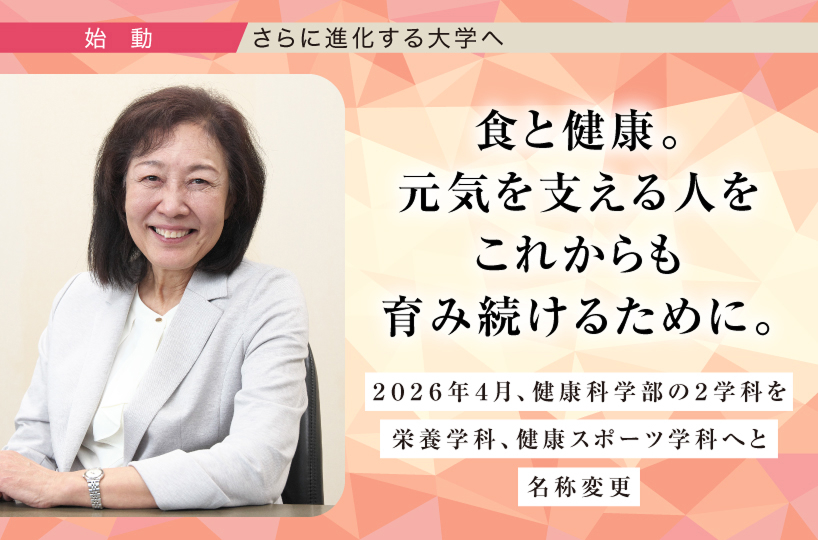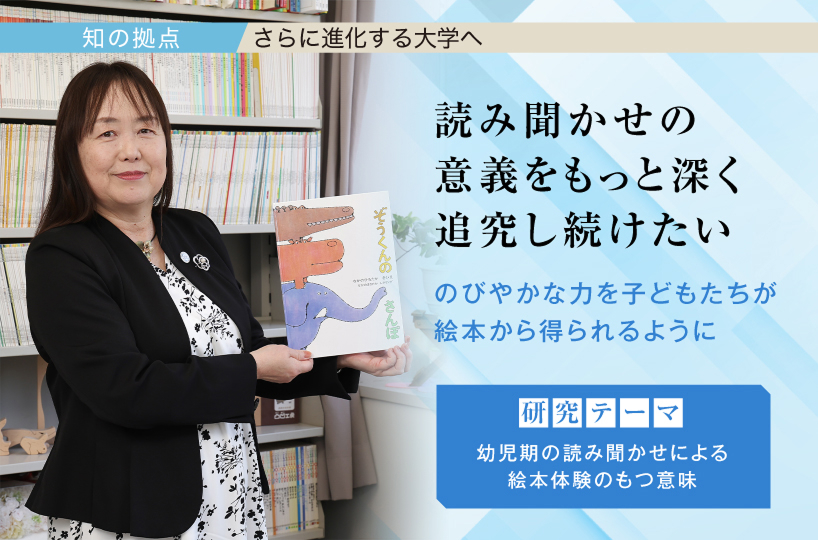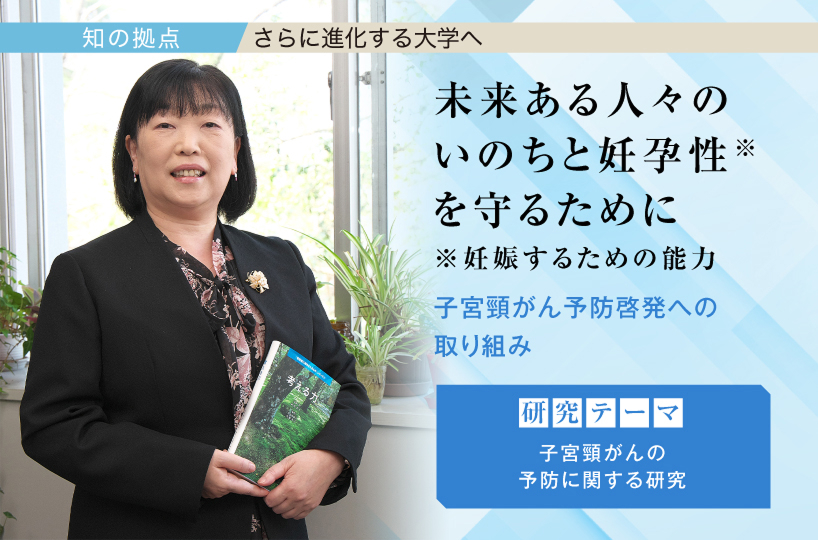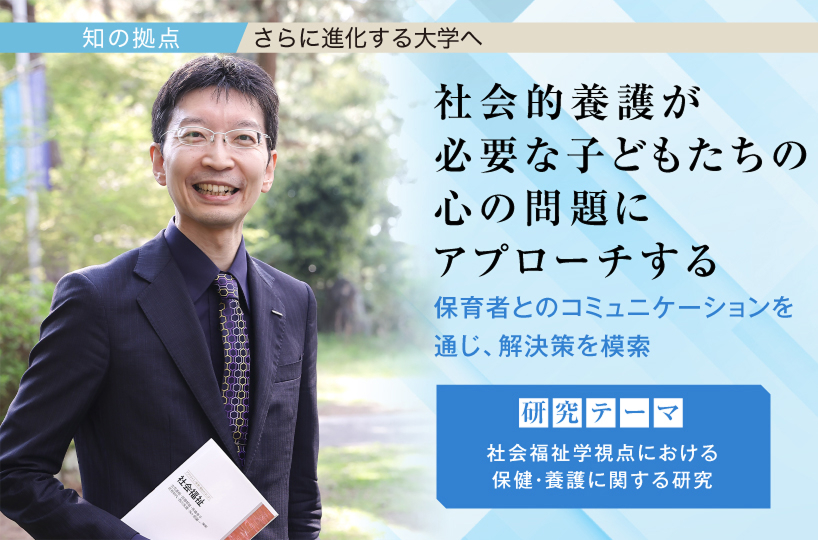地域を潤し、世界へ羽ばたく。
兵庫大学と加古川市はパートナーシップ新時代へ。
2025.07.28 vol.17学長座談会最新号
兵庫大学と、大学の位置する加古川市はグローバル化、少子高齢化、そして急速なデジタル化による激しい社会情勢の変化のなかで、大きな転換点を迎えています。これまでにも、本学は加古川市と地域創生に関する連携協定を結び、多彩な活動を進めてきましたが、今いっそう緊密な連携のもと、幅広くきめ細やかな取り組みの必要性に迫られています。
先の展望が見えにくい時代の中、大学は地域に対して何が提供できるのか。また、地域と大学は協働して何ができるのか。今号の学長対談には岡田康裕加古川市長を迎え、大学と地域が世界を視野に入れ、ともに手を携えて進むべき道を探ろうと、さまざまな視点から語り合いました。コーディネーターは、毎日新聞社営業総本部コンテンツスタジオ・ディレクショングループ(大阪)の大野靖史氏です。
目次

人口減と高齢化は、地域最大の課題
大野日本の人口減少は深刻な問題で、「100年というスパンで見ると小さな地域は消滅していく」という厳しい見方をする専門家もいます。まず、市長に加古川市の現状と課題についてお聞きしたいと思います。
岡田総務省のデータによると、令和6年10月1日現在、加古川市の人口は25万5000人弱です。ピーク時は27万近くまであったので、近年急激に減少しています。一人一人の幸福感や生活満足度を高める努力を続けるとともに、急激な減少に歯止めをかけることは差し迫った課題です。 出生率の停滞と高齢化の進行に伴い、今後も人口の自然減は続くと考えられます。そうなると2つの課題が表面化します。1つ目は超高齢社会の進行により、介護人材不足が深刻化すること。2つ目は若い人の都市部への流出です。年々減少していく20~24歳の人たちに、いかに地域や大学の魅力を知ってもらい、戻って来てもらえるかが重要です。
河野中でも22歳ぐらいまでの若年層は、ちょうど大学生の年代にあたります。この層が減ると、大学経営は従来と同じやり方では成り立ちません。 若者の流失を食い止めることは、大学の地域における役割の一つだと思います。
大野一方では、元気なシニア層が拡大すれば、引退してからも学びたい人の数も増えてくるということですね。
岡田生涯学習を続ける方が倍増するかもしれません。ヨーロッパでは年齢を重ねてから大学で学び直すのは普通のことです。我が国もそういう方向に変わっていくかもしれません。
河野我々は今後、シニア層、中でも現役世代にリスキリングプログラムやリカレント教育を積極的に提供することが重要だと考えます。リスキリングの鍵はオンラインの活用です。
より広範な関係強化で、地元に留まる学生を増やす

大野話を戻すと、若年層の流失に歯止めをかけるために大学は何ができるでしょうか。
河野まず、多くの学生を受け入れて加古川で学んでもらうことですね。そして卒業者を地元に根付かせることで、若年層人口の流失を防ぐ役割を果たせるかもしれません。
大野卒業者を地元に還元させるためには、若い人の雇用の場も必要ですよね。
河野そのためにも、大学は今後、行政や産業界とより密接な関係を結ぶ必要があると思います。
岡田市としても、地域の大学との関係を深めることは大きなチャンスにつながると考えます。現在、加古川市独自の事業として、奨学金の返還支援制度があります。市内在住の方が市内の中小企業等に就職した場合、今年度からは年間最大12万円を6年間返済する支援があります。県も奨学金の返済を支援する事業者を支援する制度を始めたので、今はダブルで支援を受けられる状態にあります。また市は、ハローワークとともに地元の企業を紹介するジョブフェア(合同就職面接会)を開催しています。
河野学生や卒業生は市の制度を積極的に活用しています。 ありがたいことです。
大野ところで、学生たちの地元志向は強いですか。
河野本学の学生は地元出身者が多く、3分の2の学生は県内に残ります。生まれ育ったまちへの愛着を語る学生も多いです。
岡田JRの駅から通学する学生が多いので、若者にとって魅力ある地域にしていこうと、加古川駅周辺や公園の再整備などを行っています。東加古川駅の北にある総合文化センターエリアのリニューアル構想も進めています。
河野高校生にも加古川の魅力を知ってもらえるよう、県立高校との高大連携協定の中で、加古川をフィールドにした体験学習を展開しています。課題解決型学習を通して地元への親近感を高め、ここで生き、ここで働こうという意欲を高めたい。さらに、地元企業の課題解決に学生が取り組む授業もありますが、これは加古川市と連携して、市のプログラムとして推進できれば面白いと思います。
岡田ぜひ、力を合わせていきましょう。地元の学生が地元企業に関わり、「ここで役に立てる」と体験できれば、地元に残りたい、住みたいと思うようになるでしょう。
協働で地域創生に弾みを
河野兵庫大学はすでに研究成果を地元に提供したり、学生がボランティアとして参加したりと、多岐にわたりさまざまな行政計画に参加させていただいています。一歩進んで、大学を地域創生の大きなパートナーとみなしていただけるなら、もっと多様な事業者を巻き込みながら、タイアップしてまちづくりや地域創生に取り組めます。 今、国は地域創生、地方創生に関してさまざまな補助金を出し、産官学連携による地域全体の取り組みを望んでいるようです。国の補助金は推進のエンジンになり得ます。我々は市と共同で申請し、補助金を活用して事業を進めたいと考えています。
岡田市としても、国の補助制度を生かせる事業内容を具体的に検討していきます。
グローバル市場を意識した教育プログラムの構築
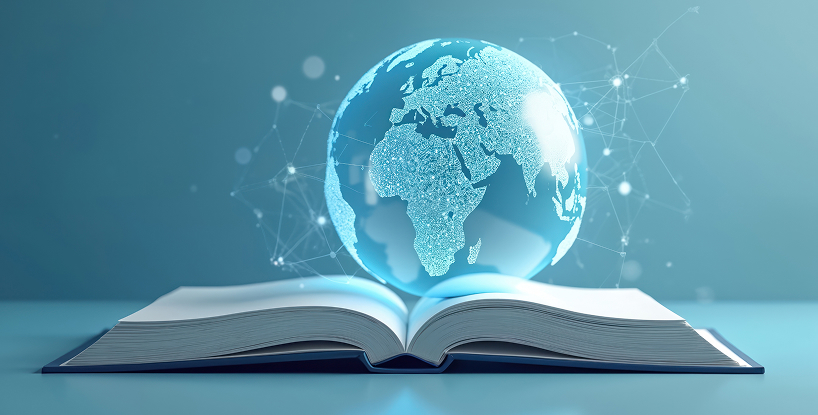
大野ここで視線を世界に広げたいと思います。
河野私たちはグローバルマーケットを意識し、海外からの学生を受け入れるだけでなく、教育プログラムを海外に輸出することも検討しています。 アジア社会では、福祉、医療看護、健康、教育といった分野の需要が高い。例えば、中国やタイでは生活習慣病が大きな社会課題となっているので、栄養、運動に関する教育機関には我々のノウハウを提供できます。また、日本流の幼児教育や、介護に関するノウハウを提供していくニーズもあると思います。 今、力を入れているのはアジアの教育機関との連携協定です。例えば相手校のカリキュラムの1/3を我々が受け持つ。メインはオンライン授業とします。AIによる同時翻訳技術が進んでいるので、言葉の問題はかなり解消されていると思います。
大野面白いですね。どこまで進んでいるのですか。
河野パートナー探しを進めているところで、できれば令和8年ぐらいをめどに事業化をと考えています。まずはニーズが明確にある幼児教育の分野から始めます。
岡田今後のグローバルな展開を期待しています。
日本語教育ニーズの高まりに応える

大野加古川市のグローバル化の現状はどうでしょう。
岡田加古川市外国人住民数は増加しており、令和6年10月1日時点で3783人です。民間企業さんが努力した結果、労働者が増えています。
最近人口の伸びが著しいのはベトナム国籍の方で、同日付で926人です。あとは韓国、中国、フィリピン、ブラジル、インドネシア、ネパール、ミャンマーなどです。
労働者の家族として来日した方のなかには、日本語ができない方もいらっしゃいます。学校現場にも、突然シリアの方など、言語が分からない方が来られることがあります。学校は教員の配置人数を調整し、翻訳機を貸し出すなど、努力をしていますが、今後ますます増えてきた時にどう対処するかが課題です。
国際交流協会には日本語を教えるボランティアが100名以上おられて、平日の夜や週末に日本語指導の教室を行っています。しかし、小さい頃からきちんと日本語を学びたいとなると、インターナショナルスクールは少なく、市で新たに設置・運営することも難しいです。大学などが誘致してくれるとありがたいですが、学生の皆さんが国際交流に関わってくださることもうれしいです。
河野兵庫大学の外国籍留学生は50名程度で、今はほぼ全員現代ビジネス学部にいますが、今後は栄養、福祉、看護などでも増えてくるでしょう。栄養と運動、福祉とビジネスなどを組み合わせたカリキュラムを構築できれば、留学生はさらに増えてくると思います。
その際キーになるのは留学生の日本語教育です。半数以上は日本で就職したい人なのですから、岡田市長も指摘されたように、日本語教育を強化する必要があります。留学生向けに、1、2年でビジネス会話レベルまで到達できるプログラムを提供し、地域住民の日本語習得ニーズもすくい取れるような仕組みを作っていくことができればと思います。
岡田在留外国人が兵庫大学でオンラインも使いながら日本語レッスンを受ける、そんな風になっていくといいですね。
地域で活躍する留学生たち
河野国際交流では、こんな事例もあります。加古川在住のブラジル国籍の学生が、タイに留学中、留学先のマハサラカム大学と、本学との提携関係にあるブラジルのマリンガ大学との提携の橋渡しをしてくれたのです。外国系学生のポテンシャルの高さを感じます。
岡田まさにグローバル時代ですね。以前、兵庫大学に在籍されていたブラジル関係の方は市の国際交流イベントを手伝ってくださり、姉妹都市のブラジル・マリンガ市から訪問団が来た際には、公式通訳まで務めてくれました。
大野労働者として来日した家族の子どもたちが日本語を勉強して、それぞれの母国の言葉と日本語の両方をしゃべりながら国際交流するという形が、どんどん活発になってくる可能性がありますよね。
海外人材も地域創生の力に
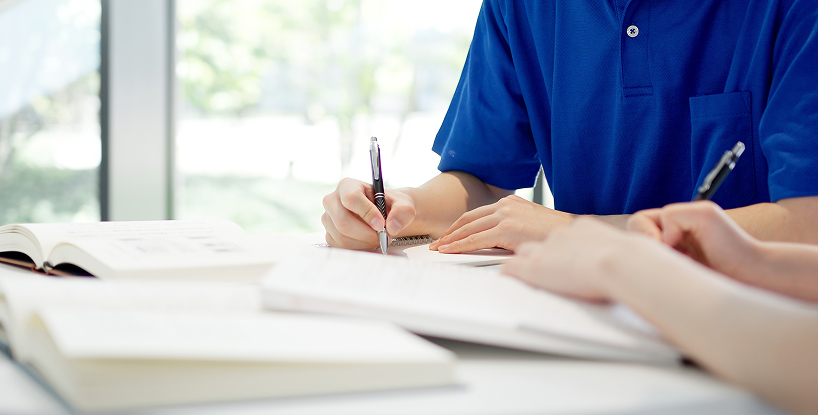
大野海外人材についての考えを聞かせてください。
河野今、本学で起こりつつあることを紹介します。自国で看護の有資格者であるベトナム人学生に対して、日本の福祉系の法人が、4年間学んだ後にその法人に就職するという条件のもとに学費を出し、社会福祉士と精神保健福祉士の資格を取得してもらうという話がまとまっています。この学生は将来、専門職として仕事をしながら幹部候補生になり、ベトナムからの人材発掘の窓口として活躍するかもしれない。これは本人にとっても、大学にも、事業者にも嬉しい、三者ウィンウィンの関係ですね。
日本はこれから外国人就労者にかなり依存しないと回っていかない社会になってきます。特に高齢化対策の分野はそうです。こういった事例は今後、特に介護人材が不足している地方では増えてくると思い
岡田地方創生においても、海外からの人材が地域に溶け込み、労働力として活躍していただく。地方創生というと地方の日本人だけの話題のように受けとられがちですが、人手不足は大きな課題ですから。
大野すごいですね。外国人もいっしょに地域活性化というのは。独創的だと思います。
自分に自信をもち、ポジティブに社会と関わっていける人材の育成を

大野そういう学生が増えてくると、周りの日本人の学生にも刺激になりますよね。大学は今後、どのような人材育成を目指しますか?
河野人材育成において大切にしているのは「人間力」と「応用力」です。応用力とは、実践力をPBL型学習や地域での学びを通じて養う。特に企業との繋がりを密にして、学生の学びの場を多く創出したいと考えています。人間力は、「和」の精神を具現化するための感謝の心。将来ヒューマンサービスに携わる学生が多いので、人の痛みが分かり、人の心情を自分ごととして捉えられる心が大切です。
大野人材育成の基本は、やはり「和」の精神ですね。
河野はい。そして今日はそこに、もう1つポイントをつけ加えたいと思います。本学の学業や課外活動、就職活動などを通じて、驚くほど成長する学生がいるのですが、私たちは、彼らが4年間でどう成長したのかを科学的に分析し、指導に活用するため、現在精緻なデータベースを構築しています。これを活かし、学生の成長を促すスイッチになった要因を明確化しようとしています。これまでにはっきりしているのは、自己効力感が重要だということです。
自己効力感は、コンプレックスを抱えていた学生が、いくつかの教育プログラムを体験する中で「よし、頑張ろう」と思う、その瞬間と関係していて、そこから成長が加速するようなのです。その成長を可視化できれば、本学の教育の成果を外部に発信できます。これは、日本の大学の中でもトップクラスの取り組みだと考えています。
大野学生が成長する要因を可視化する。このような取り組みは初めて聞きました。
岡田大変面白い取り組みですね。我々は市の総合計画において「夢と希望を描き 幸せを実感できるまち かこがわ」を掲げ、その実現に向けて「地域幸福度(ウェルビーイング)」に関する調査を令和4年から、全国に先駆けて実施しています。そこで分かってきたのですが、「健康状態」と並んでウェルビーイングと相関関係の高い項目が「自己効力感」です。つまり自己効力感が高い人は幸福度が高い。
学生時代にいろんなことにチャレンジして高い自己効力感を持てれば、社会人になってからもいろいろな課題に前向きに取り組むことができるようになるでしょう。「自分はできる」という自信がつくような体験や挑戦の機会を、大学はさまざまな形で数多く作ってあげてほしいと思います。
河野学生が自己効力感をもつきっかけは、学業、スポーツだけでなく、地域の人との関わり、起業、ボランティア活動など実に多様です。こうしたポジティブな体験を通じて大勢の学生が成長し、明日の加古川を担う人材に育っていってほしいですね。これからも、もっともっと多くの人が地域で輝けるよう、ともに挑戦を続けましょう。
- 学長座談会
- 地域
- 教育
- 留学生

岡田 康裕おかだ やすひろ
2009年から2012年に衆議院議員を務めたのち、2014年7月より加古川市長に就任。現在3期目。

コーディネーター
大野 靖史おおの やすし
毎日新聞社営業総本部 コンテンツスタジオ・ディレクショングループ(大阪)